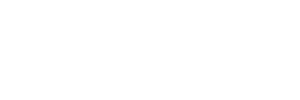【番外編】豊中市社会福祉協議会 勝部麗子さん(前編)
第2回トップインタビューの㈱プロアシストの木下社長のお話の中で、孤独死の壮絶な現場について知りました。以来ずっと、私たちの生活のすぐ隣で孤独死が起こっているという事実がずっと心に引っかかっていました。考えていくうち、一人で亡くなる方がいることが問題なのではなく、亡くなってから何週間も周りの人に気づいてもらえないぐらい社会的に孤立していることが問題なのだと考えるようになりました。私たちにできることは何なのか。考えていく中で、豊中の社会福祉協議会に社会的孤立と戦う女性がいると伺いました。日本のコミュニティーソーシャルワーカーのトップランナー、勝部麗子さんです。コミュニティーソーシャルワーカーの生みの親でもある勝部さん、その活動は、自身をモデルにしたNHKドラマ『サイレント・プア』や『プロフェッショナル 仕事の流儀』で日本中に広く知られています。社会的な孤立を防ぐために、私たちにできることは何なのか。勝部さんにお話しを伺いました。


社会福祉協議会入会のきっかけ
──トップインタビューは人を大切にする組織の長を担う皆様に、リーダーシップの要諦をお伺いする趣旨でスタートしたのですが、インタビューを通じて孤独死の問題について考えるきっかけをいただきました。色々と考える中で、高齢者が一人で亡くなる事が問題なのではなく、お亡くなりになっても誰も気づいてあげられないような社会的孤立こそが問題だと思い至り、勝部さんの活動を知りました。今日は、勝部さんが社会福祉協議会で行ってきた活動の経緯とその想いについてお話をお伺いし、私たちに何ができるのかを考えるヒントにしたいと思っています。本日はよろしくお願いいたします。
勝部:こちらこそよろしくおねがいします。

──まず、勝部さんが社会福祉協議会に飛び込んだ経緯について教えていただけますか?
勝部:実は私、大学の時は教員志望だったんです。それで、教育実習に行った時に考えさせられる出来事があったんです。
クラスにいつも忘れ物してくる子がいたんですが、「授業にならないから忘れ物をするな」って教員から毎日指導を受けるんですよ。私はどうして毎日怒られているのに忘れ物が治らないんだろう、って不思議に思っていました。
それで「なんで何回も忘れちゃうの?」ってこっそり聞いてみたんですよ。年齢が近かったこともあってか彼は本当の理由を教えてくれました。その子の家庭は今で言うゴミ屋敷だったんです。必要なものを持っていかないといけない気持ちはあるのですが、どこに何があるかわからない。
遅刻ばっかりしてくる子もいました。聞いてみたら「うちのお母さん朝まで働いてんねん。それから寝るから朝どうしても起きられへんねん」って、言うんです。朝方まで働きに出ているお母さんの帰りを待っているから夜寝られない。これらのことは果たして子供の責任なのでしょうか?
私はこういう人を助けられるのは教師ではない、福祉だろうと思いました。それで今度は市役所の福祉事務所というところに実習に行ったんです。福祉事務所っていうのは福祉制度を運用して困窮している人を助ける組織です。
例えば高齢者なら65歳以上が制度の対象になります。となると、地域で63歳の人が身体が弱っていても、助ける方法がないんです。もちろん若年性認知症だとか、他の病気がないかとかいろいろ調べて、制度に当てはめられるように努力するのですが、高齢者じゃないから高齢者対象の福祉は受けられません。障害者の定義に当てはまらないから支援が受けられないとか、住民票を豊中に移してないから助けることができない、とか福祉制度のはざまにおられて救えない人達を沢山目の当たりにしました。
制度って結局、当てはまる人にとってはすごくいいんだけど、当てはまらない人たちにとっては敷居の高いものになることがあります。64歳の人も65歳の人も弱っているのは一緒なのに、64歳だと介護保険は使えない。こういう人は「申し訳ないけど行政では助けることができません」とお伝えするしかありません。
目の前に苦しんでいる人がいるのに助けられない、制度の矛盾を目の当たりにして、どうしたらいいのかと悩みました。そんな時、社会福祉協議という組織があることを知ったんです。社会福祉協議会は、住民と一緒に福祉を作っていく所だと教えてもらいました。悩んでいた私には、それがとてもクリエイティブで面白いと感じられたんです。それで自分が生まれ育った豊中の社会福祉協議会で働こうと思ったんです。
クラスにいつも忘れ物してくる子がいたんですが、「授業にならないから忘れ物をするな」って教員から毎日指導を受けるんですよ。私はどうして毎日怒られているのに忘れ物が治らないんだろう、って不思議に思っていました。
それで「なんで何回も忘れちゃうの?」ってこっそり聞いてみたんですよ。年齢が近かったこともあってか彼は本当の理由を教えてくれました。その子の家庭は今で言うゴミ屋敷だったんです。必要なものを持っていかないといけない気持ちはあるのですが、どこに何があるかわからない。
遅刻ばっかりしてくる子もいました。聞いてみたら「うちのお母さん朝まで働いてんねん。それから寝るから朝どうしても起きられへんねん」って、言うんです。朝方まで働きに出ているお母さんの帰りを待っているから夜寝られない。これらのことは果たして子供の責任なのでしょうか?
私はこういう人を助けられるのは教師ではない、福祉だろうと思いました。それで今度は市役所の福祉事務所というところに実習に行ったんです。福祉事務所っていうのは福祉制度を運用して困窮している人を助ける組織です。
例えば高齢者なら65歳以上が制度の対象になります。となると、地域で63歳の人が身体が弱っていても、助ける方法がないんです。もちろん若年性認知症だとか、他の病気がないかとかいろいろ調べて、制度に当てはめられるように努力するのですが、高齢者じゃないから高齢者対象の福祉は受けられません。障害者の定義に当てはまらないから支援が受けられないとか、住民票を豊中に移してないから助けることができない、とか福祉制度のはざまにおられて救えない人達を沢山目の当たりにしました。
制度って結局、当てはまる人にとってはすごくいいんだけど、当てはまらない人たちにとっては敷居の高いものになることがあります。64歳の人も65歳の人も弱っているのは一緒なのに、64歳だと介護保険は使えない。こういう人は「申し訳ないけど行政では助けることができません」とお伝えするしかありません。
目の前に苦しんでいる人がいるのに助けられない、制度の矛盾を目の当たりにして、どうしたらいいのかと悩みました。そんな時、社会福祉協議という組織があることを知ったんです。社会福祉協議会は、住民と一緒に福祉を作っていく所だと教えてもらいました。悩んでいた私には、それがとてもクリエイティブで面白いと感じられたんです。それで自分が生まれ育った豊中の社会福祉協議会で働こうと思ったんです。

社会福祉協議会とは

──目の前の人を助けたい、という想いが勝部さんを社会福祉協議会に導いたのですね。「住民と一緒に福祉をつくる」とは具体的にどのようなことをするのでしょう。
勝部:元々、豊中の社会福祉協議会は小学校の校区ごとにコミュニティー組織を作っていて、そこでいろいろなイベントを開催したり、敬老会のような事業活動をしていました。助けなければいけない方々を、イベントを通じてコミュニティーで緩やかなつながりができる仕組みを社会福祉協議会は作り上げていました。
阪神淡路大震災をきっかけにして活動はイベント開催から、ボランティアの方々と一緒に、支援が必要な方々を能動的に見守るという活動にシフトしていきました。
阪神淡路大震災をきっかけにして活動はイベント開催から、ボランティアの方々と一緒に、支援が必要な方々を能動的に見守るという活動にシフトしていきました。
──変化のきっかけは何だったのでしょう?
勝部:阪神淡路大震災で豊中は大阪の中で最大の被災地になったのですが、震災直後から要支援者に支援の手が差し伸べられる地域がある一方で、半年経っても電気の傘がひっくり返ったままになっていたり、タンスが倒れたままになっている、というような話が入って来る地域もありました。
──地域によって支援のレベルに大きな差があったのですね。
勝部:はい。さらに大きな問題もありました。それは孤独死です。
家を失った皆さんはまず避難所に行き、その後仮設住宅に行って、復興住宅に移っていかれます。震災直後に入る避難所ではプライバシーは確保できない代わりに、近所の方同士なので、例えば「ここのおばあちゃんって奥ゆかしい人やから、率先してお弁当取りに行ったりしはれへん。おばあちゃんの分も取ってきてあげたよ」と言って、運んでくれる人がいたりと、濃密なコミュニケーションがありました。
しかし、復興が進んで仮設住宅に生活のステージが移ると、【孤独死○○人】って、新聞に毎日毎日出るようになりました。仮設住宅は抽選なので、避難所にあった人間関係性はバラバラに解体されてしまいます。みんな違うところへ行かされて、そこでは人間関係ができにくい。避難所から仮設住宅、仮設住宅から復興住宅に移っていくその過程で、被災者は何度も何度もコミュニティーを失うのです。
「家は与えられたけども、その中でぽつんと暮らす」。声をかけてくれる人も誰もいない。特に50代ぐらいの人はアルコール依存になられる方がすごく増えました。そういう状況で起こったのが、孤独死です。孤独の中で亡くなり、たとえ死んだとしても誰も訪問をしてくれない。
それまでは「住宅を与えたらみんな人はなんとか生きていける」っていう風に思われていました。家さえあれば…避難所よりもプライバシーが守られたら幸せになると思われていた。しかし、そうではありませんでした。
人って、繋がりがなくなったら死んでいくんです。それを目の当たりにしました。震災を通じて、人間にとって、人との繋がりがいかに大切なことかを知りました。
家を失った皆さんはまず避難所に行き、その後仮設住宅に行って、復興住宅に移っていかれます。震災直後に入る避難所ではプライバシーは確保できない代わりに、近所の方同士なので、例えば「ここのおばあちゃんって奥ゆかしい人やから、率先してお弁当取りに行ったりしはれへん。おばあちゃんの分も取ってきてあげたよ」と言って、運んでくれる人がいたりと、濃密なコミュニケーションがありました。
しかし、復興が進んで仮設住宅に生活のステージが移ると、【孤独死○○人】って、新聞に毎日毎日出るようになりました。仮設住宅は抽選なので、避難所にあった人間関係性はバラバラに解体されてしまいます。みんな違うところへ行かされて、そこでは人間関係ができにくい。避難所から仮設住宅、仮設住宅から復興住宅に移っていくその過程で、被災者は何度も何度もコミュニティーを失うのです。
「家は与えられたけども、その中でぽつんと暮らす」。声をかけてくれる人も誰もいない。特に50代ぐらいの人はアルコール依存になられる方がすごく増えました。そういう状況で起こったのが、孤独死です。孤独の中で亡くなり、たとえ死んだとしても誰も訪問をしてくれない。
それまでは「住宅を与えたらみんな人はなんとか生きていける」っていう風に思われていました。家さえあれば…避難所よりもプライバシーが守られたら幸せになると思われていた。しかし、そうではありませんでした。
人って、繋がりがなくなったら死んでいくんです。それを目の当たりにしました。震災を通じて、人間にとって、人との繋がりがいかに大切なことかを知りました。
──住環境以上に、人との繋がりが人間を生かすのですね。
勝部:介護を利用しないといけないような状態の人には普段からヘルパーさんが来てくれますが、普通に生活している人たちは、身体は元気でも孤独になりやすい。亡くなっても誰にも気づかれないような状況が頻繁に起きていました。
その時に、私たちはイベントでなんとなく繋がっているだけではいけない。「ひとりひとりをちゃんと見守る」体制を作っていく必要がある。そう考えて震災の翌年から、各小学校単位の見守り体制を「小地域ネットワーク活動」という名前できっちり組織することにしました。
その時に、私たちはイベントでなんとなく繋がっているだけではいけない。「ひとりひとりをちゃんと見守る」体制を作っていく必要がある。そう考えて震災の翌年から、各小学校単位の見守り体制を「小地域ネットワーク活動」という名前できっちり組織することにしました。
──どんな方を見守るのですか?
勝部:ひとり暮らしお年寄りの方が多いですね。あとは小さい子供さんを抱えて悩んでいる方もおられます。最近では老々介護に関する相談も多いですし、少し引きこもりがちのお子様の見守りをされている地区もあります。そのような見守り対象の方が豊中には1万2000世帯いらっしゃいます。見守りと同時に、高齢者にお弁当を届けたり、子育てサロンをつくったり、子ども食堂を立ち上げたり「ひとりぼっちを作らない」取り組みを行っています。
たくさんのボランティアさんの助けもあって大阪北部地震の時には4時間で見守り対象者の安否確認をすることができました。
たくさんのボランティアさんの助けもあって大阪北部地震の時には4時間で見守り対象者の安否確認をすることができました。

ボランティアを増やす取り組み

──12,000世帯の安否確認を4時間で終えるのは並大抵のことではありませんね。どのような体制で見守り活動を行われているのでしょう?
勝部:各小学校区単位でボランティアの組織を作っています。校区福祉委員会という組織を作っていまして、そこには地元で普段から協力いただけるようなボランティアの方が、平均すると80〜100人ぐらい各小学校区におられます。その方々が日常的に見守りをしています。
災害のための安否確認の訓練も年に2回は行います。見守り対象の方の家に出向いて行って安否確認をする作業も、常にやってきています。(コロナで一部中断しているところもありますが)
ひとりぼっちにならないためのいろんな仕組みっていうのは、すべて専門職で支えていくのはコストのかかることですし生活圏的での自然に気遣いあえる関係作りは行政ではなかなか作ることが難しい。だからボランティアの力が重要です。ご近所で見守り多少の方を気遣ってくれるような人を1人でも2人でもつくることができれば、ひとりぼっちの人たちが元気になれる。そういう組織づくりです。
阪神淡路大震災以来ずっと取り組んできた見守り活動は、今や8000人のボ方がボランティアとして参加するようになりました。見守り対象の方に何かあればあちこちのボランティアからご相談があるというような体制になってきたんです。
災害のための安否確認の訓練も年に2回は行います。見守り対象の方の家に出向いて行って安否確認をする作業も、常にやってきています。(コロナで一部中断しているところもありますが)
ひとりぼっちにならないためのいろんな仕組みっていうのは、すべて専門職で支えていくのはコストのかかることですし生活圏的での自然に気遣いあえる関係作りは行政ではなかなか作ることが難しい。だからボランティアの力が重要です。ご近所で見守り多少の方を気遣ってくれるような人を1人でも2人でもつくることができれば、ひとりぼっちの人たちが元気になれる。そういう組織づくりです。
阪神淡路大震災以来ずっと取り組んできた見守り活動は、今や8000人のボ方がボランティアとして参加するようになりました。見守り対象の方に何かあればあちこちのボランティアからご相談があるというような体制になってきたんです。
──豊中は40万人都市ですが、その中で8000人のボランティアの方々がいらっしゃるということは50人に1人。すごい動員力ですね。
勝部:実は私は、社会福祉協議会に入った時「ボランティアセンター」に配属されたんです。センターっていうぐらいだから立派な建物があるかと思ったら、「はい、これが君の机」って言われて。「ボランティアの人はどこにいるんですか?」って聞いたら、「それを探すのが君の仕事」って(笑)。ボランティアゼロ、机一つからのスタートでした。
ボランティアって名札をつけて歩いているわけじゃないから、こんな40万人都市の中で実際にボランティアをやってくれる人をどうやって探し出せばいいのだろう、と最初は途方にくれました。それに活動できるのは私ひとりです。だから最初は小さなことから始めました。高齢者のことが好きでお話し相手やったらできるっていう方がおられたら、「電話で声かけするグループを作ったらどう?」。車を出せる方がおられたら「車椅子で4人まで送り迎えするグループ作ったらいいんじゃない」とか。そのようにしてお困りの人と貢献できる人をマッチングするコーディネーターのようなことをして少しずつボランティアの輪を広げました。そこで皆さん、人が元気になっていく姿を目の当たりにするんです。
例えば、隣に引きこもりのお兄ちゃんがいた住民の方は、迷った挙句、社会福祉協議会に連絡をくださいました。私たちのいろんな活動を通してそのお兄ちゃんが元気になって、自転車にて外に出ている姿を見かけるようになるとその方は「よかったなぁ。」と思ってくれます。思うだけじゃなくて「じゃあまた探してやろうか」と見守りボランティアに参加してくれるようになります。
人が元気になっていく姿とか、蘇っていく姿を目の当たりにすることが人間の行動を生んでいきます。そのような往復をしながら地域がだんだん耕されていくのです。
ボランティアって名札をつけて歩いているわけじゃないから、こんな40万人都市の中で実際にボランティアをやってくれる人をどうやって探し出せばいいのだろう、と最初は途方にくれました。それに活動できるのは私ひとりです。だから最初は小さなことから始めました。高齢者のことが好きでお話し相手やったらできるっていう方がおられたら、「電話で声かけするグループを作ったらどう?」。車を出せる方がおられたら「車椅子で4人まで送り迎えするグループ作ったらいいんじゃない」とか。そのようにしてお困りの人と貢献できる人をマッチングするコーディネーターのようなことをして少しずつボランティアの輪を広げました。そこで皆さん、人が元気になっていく姿を目の当たりにするんです。
例えば、隣に引きこもりのお兄ちゃんがいた住民の方は、迷った挙句、社会福祉協議会に連絡をくださいました。私たちのいろんな活動を通してそのお兄ちゃんが元気になって、自転車にて外に出ている姿を見かけるようになるとその方は「よかったなぁ。」と思ってくれます。思うだけじゃなくて「じゃあまた探してやろうか」と見守りボランティアに参加してくれるようになります。
人が元気になっていく姿とか、蘇っていく姿を目の当たりにすることが人間の行動を生んでいきます。そのような往復をしながら地域がだんだん耕されていくのです。
──ボランティアの数を増やしていく中で大変だったことは何ですか?
勝部:最初の頃は、「そんなこと行政がやったらいいのに、なんであんたらがそんな余計なことまですんの」みたいな話もありました。でも、ひとりで抱え込まずにみんなで知恵を集めていくというやり方をしていたので、大変ではなかったですが。いや、その時は大変だと思っていたはずですが、こうやって振り返ると楽しい事ばかりだったように思います。
──活動する人が簡単には増えない中で、ずっとやり続けられた原動力はなんですか?
勝部:やっぱり目の前の1人です。目の前に苦しんでいる人がいるっていうことは紛れもない事実で、ごまかしようがない。
最初の頃、地域で引きこもりの人たちの支援や、「子供食堂が必要です」と話しに行った時に、「何人の子が大変なんや」って言われました。1人の子供の事が心配で、この子を助けてあげたいと言うと、なんでその子だけ助けるんだって言われました。でも一人だけだから助けない、たくさんの人が苦しんでいるなら助けようって言う人って、結局困っている人が何パーセントになっても助けないんです。ただのやらない理由です。
若い頃は、その「何人の子供が大変なんや」という指摘に対抗できる資料が必要だと思っていました。でもよく考えると、たかだか我々素人のボランティアがやることです。子供食堂に何百人も来られたらパンクしてしまいます。小さくても活動をしていると、今まで反対していた人ですら「俺ら、ええことしてるやん」とおっしゃいます。
取り組みを体験して、共感した人たちが活動を広げていき、同じような状況にある沢山の子供たちを助ける仕組みがつくられていくのです。だから最近は難しい話はせず、「1人の子を助ける取り組みを通じて、地域全体が優しくなっていくっていうことにチャレンジしませんか」と言うようにしています。体験で人の心は変わるのです。
最初の頃、地域で引きこもりの人たちの支援や、「子供食堂が必要です」と話しに行った時に、「何人の子が大変なんや」って言われました。1人の子供の事が心配で、この子を助けてあげたいと言うと、なんでその子だけ助けるんだって言われました。でも一人だけだから助けない、たくさんの人が苦しんでいるなら助けようって言う人って、結局困っている人が何パーセントになっても助けないんです。ただのやらない理由です。
若い頃は、その「何人の子供が大変なんや」という指摘に対抗できる資料が必要だと思っていました。でもよく考えると、たかだか我々素人のボランティアがやることです。子供食堂に何百人も来られたらパンクしてしまいます。小さくても活動をしていると、今まで反対していた人ですら「俺ら、ええことしてるやん」とおっしゃいます。
取り組みを体験して、共感した人たちが活動を広げていき、同じような状況にある沢山の子供たちを助ける仕組みがつくられていくのです。だから最近は難しい話はせず、「1人の子を助ける取り組みを通じて、地域全体が優しくなっていくっていうことにチャレンジしませんか」と言うようにしています。体験で人の心は変わるのです。

──「一人を助ける活動」を通じて共感の輪を広げていったのですね。
勝部:はい、そのような活動を通じてボランティアの方が増えていきました。ボランティアの方が増えると地域の困りごとを見つける「目」が増えていきます。
例えばこのコロナ禍で、ホームレスの人が服部緑地公園で増えていることってご存知ですか?実は彼らは朝やお昼に行っても会えないんです。人目を気にして人が増える前にいなくなってしまう。知らなければ私たちには見つけられません。このことは早朝ラジオ体操に行っているボランティアの人たちが見つけて教えてくれたんです。「勝部さん、早朝に行ってみなさい」ってね。
で、実際に行って「どうしたの」って聞いたら、コロナで減収してローンが返せなくなったと仰います。「自分が悪いからもうどうでもいいや」「自己責任ですわ」って言っている人に、「いやいや、再チャレンジしていくための仕組みがあるから」とか、「定額給付金10万円もらえるからそれで住居設定したら、それで生活できるようになるから」とかお話しすると、生活の再建の目途が立っていきます。そんな方々を、この2年で30人ぐらい助けることができました。
例えばこのコロナ禍で、ホームレスの人が服部緑地公園で増えていることってご存知ですか?実は彼らは朝やお昼に行っても会えないんです。人目を気にして人が増える前にいなくなってしまう。知らなければ私たちには見つけられません。このことは早朝ラジオ体操に行っているボランティアの人たちが見つけて教えてくれたんです。「勝部さん、早朝に行ってみなさい」ってね。
で、実際に行って「どうしたの」って聞いたら、コロナで減収してローンが返せなくなったと仰います。「自分が悪いからもうどうでもいいや」「自己責任ですわ」って言っている人に、「いやいや、再チャレンジしていくための仕組みがあるから」とか、「定額給付金10万円もらえるからそれで住居設定したら、それで生活できるようになるから」とかお話しすると、生活の再建の目途が立っていきます。そんな方々を、この2年で30人ぐらい助けることができました。
──見守り活動を進める上では苦労もあったのでしょうね。
勝部:印象に残っている事件があります。つい6年ほど前なのですが、50代の娘さんが熱中症で亡くなった後ろから80代のお父さんが白骨で出てきたというセンセーショナルな事件が豊中で起こりました。
その時に、見守り活動をこれだけやっていた豊中で、どうしてこういう事件を防げなかったんだと活動の在り方を厳しく問われました。今まで、お年寄りのひとり暮らし世帯とふたり暮らしであっても介護者が高齢者の世帯も見守っていたのですが、80歳の親と50歳の娘の家となると一般的な介護家庭です。見守りをやっていただいている皆さんは「業」ではなくボランタリーとしてやっていただいているんです。
そのような家庭を見てないからと言って、地域の活動の在り方が問われるということに、大変複雑な気持ちになりました。その中で、ボランティアの方々と一緒にこのような事件をどうやったら防げるかと真剣に考え、「見守りローラー作戦」を開始しました。
その時に、見守り活動をこれだけやっていた豊中で、どうしてこういう事件を防げなかったんだと活動の在り方を厳しく問われました。今まで、お年寄りのひとり暮らし世帯とふたり暮らしであっても介護者が高齢者の世帯も見守っていたのですが、80歳の親と50歳の娘の家となると一般的な介護家庭です。見守りをやっていただいている皆さんは「業」ではなくボランタリーとしてやっていただいているんです。
そのような家庭を見てないからと言って、地域の活動の在り方が問われるということに、大変複雑な気持ちになりました。その中で、ボランティアの方々と一緒にこのような事件をどうやったら防げるかと真剣に考え、「見守りローラー作戦」を開始しました。
──こちらから地域の方々を訪問する活動ですね?
勝部:はい。アウトリーチと言って、こちらから支援対象者を訪問する活動です。でも簡単ではありません。自治会に入ってない人が今増えていますし、ここ向こう3軒の人の顔を知らない人たちも多いです。外国人労働者もとても多いです。地域住民だからって言っても、突然「こんにちは」って訪問することは難しいです。
だから、私たちのようなコミュニティーソーシャルワーカーっていう専門職が1件1件ボランティアの方と一緒に訪問して、何か心配なことがあったり、お困り事があったら相談してくださいねとお話しして回ります。そのようにして年間4000軒を訪問します。
だから、私たちのようなコミュニティーソーシャルワーカーっていう専門職が1件1件ボランティアの方と一緒に訪問して、何か心配なことがあったり、お困り事があったら相談してくださいねとお話しして回ります。そのようにして年間4000軒を訪問します。
──すごい数の訪問量ですね!
勝部:セールスマンよりもよく動くって言われます(笑)。で、実際に100件くらい回ると心配な人が出てきます。
ひとり暮らしで元気な方だったけれど、コロナの中で他の人との交流がなくなり、認知症が進んでいる方が出てきていたり、ふたり暮らしだと思っていたけども、いつの間にか家族葬を済まされていてひとり暮らしになっているとか、ご近所も全然ご存知ないっていうようなことが出てきたりとか。そんな方々の様子を見て心配だなと思ったら、見守り対象者にいれます。こんな風に、地道に地道に活動しています。いわば、お節介活動ですよね。
昔はそういうお節介を地域の中で当たり前のようにやっていたのですが、今はちゃんとルールがないと成り立ちません。私たちがやっているお節介は「節度あるお節介」。相手のプライバシーに配慮しながら活動しなければいけません。だから研修等を通じてプライバシーのこともちゃんと勉強してもらった上で見守り活動を推進しています。
ひとり暮らしで元気な方だったけれど、コロナの中で他の人との交流がなくなり、認知症が進んでいる方が出てきていたり、ふたり暮らしだと思っていたけども、いつの間にか家族葬を済まされていてひとり暮らしになっているとか、ご近所も全然ご存知ないっていうようなことが出てきたりとか。そんな方々の様子を見て心配だなと思ったら、見守り対象者にいれます。こんな風に、地道に地道に活動しています。いわば、お節介活動ですよね。
昔はそういうお節介を地域の中で当たり前のようにやっていたのですが、今はちゃんとルールがないと成り立ちません。私たちがやっているお節介は「節度あるお節介」。相手のプライバシーに配慮しながら活動しなければいけません。だから研修等を通じてプライバシーのこともちゃんと勉強してもらった上で見守り活動を推進しています。

──支援対象者を見つけることに大きな力を割いておられるのですね。
勝部:ローラー作戦を通じて私たちが気づいたことは、本当に困っている人たちは自分から声を出せないということです。
例えば、認知症が進んでおられる高齢者の方は、ご自身で「私認知症です」と相談には来られません。ゴミ出しの日が分からなくて、毎日間違ってゴミを出す。そういうところから近所の人が気づいてあげなければいけません。
他にも、外国人の方で、日本語でおしゃべりはできるけど、日本語が全く読めない方がおられます。だから市から支援に関する手紙が来ていても全然読めない。こういう事はデスクに座っていてはわかりません。
そういう方々に届く支援を、と考えると、こちらから声かけをすることが大切なんです。
例えば、認知症が進んでおられる高齢者の方は、ご自身で「私認知症です」と相談には来られません。ゴミ出しの日が分からなくて、毎日間違ってゴミを出す。そういうところから近所の人が気づいてあげなければいけません。
他にも、外国人の方で、日本語でおしゃべりはできるけど、日本語が全く読めない方がおられます。だから市から支援に関する手紙が来ていても全然読めない。こういう事はデスクに座っていてはわかりません。
そういう方々に届く支援を、と考えると、こちらから声かけをすることが大切なんです。
──「お節介な」ボランティアの方の裾野が必要ですね。
勝部:今、有料で頼むほどでもない、増して市役所に言うほどのことでもないけれど、ちょっと困っていることをサポートするボランティアの方を募集しているんです。例えば大型のゴミを出したいけど、ひとりだと重くて出せないとか、電球交換したいけど高いとこに上るのは怖いとか。そういう方々へのサポート、小さな助け合いです。
ボランティアの方はそういう活動を入口にして、サポートした人が本当に困っていることをもう少し深く聞いてみようと思うようになる。そういう優しい住民活動を広げていくことが狙いなんです。
私たちソーシャルワーカーには助けるノウハウもあるのですが、どこに困っている人がいるかがわからない。だから「SOSを出している人に気づく」ボランティアの人を増やしていくことが重要なのです。私が30年間やってきたことのポイントですね。
ボランティアの方はそういう活動を入口にして、サポートした人が本当に困っていることをもう少し深く聞いてみようと思うようになる。そういう優しい住民活動を広げていくことが狙いなんです。
私たちソーシャルワーカーには助けるノウハウもあるのですが、どこに困っている人がいるかがわからない。だから「SOSを出している人に気づく」ボランティアの人を増やしていくことが重要なのです。私が30年間やってきたことのポイントですね。
──ほっとけない人づくり、ですね。
勝部:そう!ほっとけない人づくりです。
*******
ここで勝部さんは室外の男性に気づかれて、慌てて離席されました。
部屋に戻ってきた勝部さんは、男性との驚くべきエピソードを教えてくださったのです。【下巻に続く】
豊中市社会福祉協議会
〒560-0023 大阪府豊中市岡上の町2-1-15
聞き手:小西敏仁(ネッツトヨタニューリー北大阪 代表取締役社長)
撮影・構成:広報室 山本一夫
撮影・構成:広報室 山本一夫