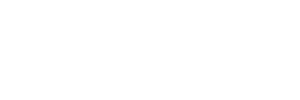株式会社キリン堂
当社の地域振興券加盟店でもあるキリン堂様。地元の皆様に愛されて、加盟店さんの中でも換金額では常にトップクラスです。
そんなキリン堂様は、2006年以降M&Aや組織改革を通して大きく成長をしてこられました。人を大切にする経営や、地域密着型のドミナント経営は私たちのお手本でもあります。単純な規模やオペレーションの効率化だけではなく、社員の成長を通して、本質的なサービス品質の向上を目指してこられた軌跡を寺西社長にお伺いしました。
そんなキリン堂様は、2006年以降M&Aや組織改革を通して大きく成長をしてこられました。人を大切にする経営や、地域密着型のドミナント経営は私たちのお手本でもあります。単純な規模やオペレーションの効率化だけではなく、社員の成長を通して、本質的なサービス品質の向上を目指してこられた軌跡を寺西社長にお伺いしました。

ーーー本日はよろしくお願いいたします。まずは御社の成り立ち、67年前にさかのぼって教えていただけますでしょうか?
寺西:当社は私の父が創業しました。父は田舎の8人兄弟の真ん中で、戦後の物資不足の中、砂糖の代用としてもてはやされていたサッカリンの合成に関心を持ち、薬学の道を志したそうです。
世の中のためになる化学合成薬品を自分の手で生み出したいという思いから、貿易社に就職し、海外の薬品情報をリサーチしたり、輸入した原料薬品を国内の製薬会社、化学薬品の企業に販売したりする仕事に従事しました。その後、当時チェーンとして隆盛を極めていたヒグチ薬局に就職しました。そこで若くして専務まで上り詰めていったのですが、小売業の素晴らしい世界を知り、小売業に命をかけようと強く決心して独立します。
競合他社として分離独立するのですから、たくさんの軋轢があったようです。仕入れ先さんや問屋さんに商品をおろしてもらえないとか。お金もコネも信用もないので、初めは本当に苦労したそうです、在庫をできるだけ少なくするために、売れた分だけ仕入れるような工夫をいつもしていました。
当時は今のようなパッケージに入った薬の他に、自家製剤と言って薬を自分で処方して軟膏を調合したりしていました。初め全然売れなかったキリン堂の薬も、「よく効く」という評判が少しずつ広がり、商売が軌道に乗っていきました。創業翌年には2号店を出すに至りました。父は「うちの薬局の薬はよぉ効いたんや。長蛇の列ができたんやぞ。」といつも言っていますね。私は見ていなんですが(笑)。そうやって少しずつ、お金も信用も蓄積されていき、1958年に株式会社に改組しました。
世の中のためになる化学合成薬品を自分の手で生み出したいという思いから、貿易社に就職し、海外の薬品情報をリサーチしたり、輸入した原料薬品を国内の製薬会社、化学薬品の企業に販売したりする仕事に従事しました。その後、当時チェーンとして隆盛を極めていたヒグチ薬局に就職しました。そこで若くして専務まで上り詰めていったのですが、小売業の素晴らしい世界を知り、小売業に命をかけようと強く決心して独立します。
競合他社として分離独立するのですから、たくさんの軋轢があったようです。仕入れ先さんや問屋さんに商品をおろしてもらえないとか。お金もコネも信用もないので、初めは本当に苦労したそうです、在庫をできるだけ少なくするために、売れた分だけ仕入れるような工夫をいつもしていました。
当時は今のようなパッケージに入った薬の他に、自家製剤と言って薬を自分で処方して軟膏を調合したりしていました。初め全然売れなかったキリン堂の薬も、「よく効く」という評判が少しずつ広がり、商売が軌道に乗っていきました。創業翌年には2号店を出すに至りました。父は「うちの薬局の薬はよぉ効いたんや。長蛇の列ができたんやぞ。」といつも言っていますね。私は見ていなんですが(笑)。そうやって少しずつ、お金も信用も蓄積されていき、1958年に株式会社に改組しました。

お客様の人生全てのステージに寄り添い、お役に立ちたい

ーーー創業当初は大変な思いをされたんでしょうね。
寺西:父はセールストークが上手なタイプではありませんでしたが、薬をつくるのが好きでした。いい商品、いいお薬を作って評判を積み上げてきたそうです。それから、とにかくよく働いたそうです。
薬屋なので、やっぱり夜に戸を叩いて薬を求めに来られる方もいらっしゃいます。当時は店の2階が住まいでしたので、必ず対応していたそうです。私が物心つくころにはキリン堂はある程度大きくなっていたので当時のことはわかりませんが、私から見ても父はよく働く人だという印象があります。
家ではいつも本を読んでいて、ゴロゴロしているところは見たことがありません。仕事の帰りも遅く、「鋼のような人やな」といつも幼心に思っていました。
薬屋なので、やっぱり夜に戸を叩いて薬を求めに来られる方もいらっしゃいます。当時は店の2階が住まいでしたので、必ず対応していたそうです。私が物心つくころにはキリン堂はある程度大きくなっていたので当時のことはわかりませんが、私から見ても父はよく働く人だという印象があります。
家ではいつも本を読んでいて、ゴロゴロしているところは見たことがありません。仕事の帰りも遅く、「鋼のような人やな」といつも幼心に思っていました。
ーーー高い技術と勤勉さを売って信頼を築いてこられたんですね。たった1店舗の薬局から、ここまで大きなチェーンを築いてこられた成功要因はどこにあるとお考えですか?
寺西:「チャレンジ」です。創業者である父は、たくさんのチャレンジをしてきました。
例えば、商流という面で父は革新的なチャレンジを行いました。今ではショッピングセンターに薬屋が出店するのは一般的ですが、キリン堂はその草分けです。1970年ごろにはジャスコさんや長崎屋さんはじめ、相当な数の店舗をショッピングセンターに出店していました。
当時は商店街に出店するのが常道だったところ、父は集客力のある施設に薬局を置くことを思いついたのです。
他にも、現在当社の看板となっている健康食品も父のチャレンジの一つです。世の中が健康食品に見向きもしていない時代から父は「健康食品を扱うんや」と言って豆乳とか、高麗人参をいっぱい家に持ってきて、家族によく飲ませていました。
しっかり利益が取れる既販の薬だけやっていたら手堅い商売ができるはずです。なぜわざわざ新しい事に取り組もうとするのか私は不思議に思っていました。でも今考えると、病気になった人だけを相手にするよりも、病気になりたくない人も相手にするビジネスのほうが、お客様の幅が広がります。そういうことが父の目には見えていました。
ビジネス上の理由だけではありません。父はいつも「生活者の役に立ちたいんや。病気になって直すのは当たり前やけど、そもそも病気になること自体が問題や。そこを変えていかなあかん。」と薬屋としての理想を語っていました。
きっかけになったのが近畿大学の有地教授という方との出会いでした。その方は漢方薬の研究されている方で、元々漢方薬に興味があった父とはすぐに意気投合し、健康に対する考え方を多く学ばせていただいたそうです。
例えば、漢方薬の考え方では、体には「気・血・水」が存在して、その気と水と血液をバランスよく整え、循環させることが健康につながる、と言われています。そこから、「気・血・水」を整える役割は漢方薬だけではなく、食品にもあるはずだ。と父は考えを進め、食事で採りきれない栄養を補えるサプリメントを研究し、販売するようになったのです。
今、キリン堂の売上を見てみると、薬の比率はどんどん減ってきています。健康食品をはじめとした未病対策商品が増えてきています。病気ではなく、積極的に健康を志向する商品を売る会社に変わってきています。当時、いち早く健康食品に取り組んだことが、キリン堂の強みの源泉になっていると思います。
例えば、商流という面で父は革新的なチャレンジを行いました。今ではショッピングセンターに薬屋が出店するのは一般的ですが、キリン堂はその草分けです。1970年ごろにはジャスコさんや長崎屋さんはじめ、相当な数の店舗をショッピングセンターに出店していました。
当時は商店街に出店するのが常道だったところ、父は集客力のある施設に薬局を置くことを思いついたのです。
他にも、現在当社の看板となっている健康食品も父のチャレンジの一つです。世の中が健康食品に見向きもしていない時代から父は「健康食品を扱うんや」と言って豆乳とか、高麗人参をいっぱい家に持ってきて、家族によく飲ませていました。
しっかり利益が取れる既販の薬だけやっていたら手堅い商売ができるはずです。なぜわざわざ新しい事に取り組もうとするのか私は不思議に思っていました。でも今考えると、病気になった人だけを相手にするよりも、病気になりたくない人も相手にするビジネスのほうが、お客様の幅が広がります。そういうことが父の目には見えていました。
ビジネス上の理由だけではありません。父はいつも「生活者の役に立ちたいんや。病気になって直すのは当たり前やけど、そもそも病気になること自体が問題や。そこを変えていかなあかん。」と薬屋としての理想を語っていました。
きっかけになったのが近畿大学の有地教授という方との出会いでした。その方は漢方薬の研究されている方で、元々漢方薬に興味があった父とはすぐに意気投合し、健康に対する考え方を多く学ばせていただいたそうです。
例えば、漢方薬の考え方では、体には「気・血・水」が存在して、その気と水と血液をバランスよく整え、循環させることが健康につながる、と言われています。そこから、「気・血・水」を整える役割は漢方薬だけではなく、食品にもあるはずだ。と父は考えを進め、食事で採りきれない栄養を補えるサプリメントを研究し、販売するようになったのです。
今、キリン堂の売上を見てみると、薬の比率はどんどん減ってきています。健康食品をはじめとした未病対策商品が増えてきています。病気ではなく、積極的に健康を志向する商品を売る会社に変わってきています。当時、いち早く健康食品に取り組んだことが、キリン堂の強みの源泉になっていると思います。

ーーー他の会社がやらないようなことをやるっていうのは、昔から御社のアイデンティだったのですね。「生活者の役に立ちたい」という思いに大変共感しました。きっと御社の社員の皆様もそうだったのでしょうね。実際、御社は現在でもヘルス&ビューティーをキーワードに健康志向のお客様に向けた様々なサービスを展開しておられます。
寺西:おっしゃる通り、価値観が大切です。私たちの考えは、地域のお客様のライフタイムバリューをどれだけ高められるかで勝負する会社になることです。地域に密着して、お客様の「生老病死」人生の全てのステージに寄り添い、お役に立ちたいと思っています。
だから当社は、企業ドメインを考えるときに、商品を絞り込むのではなくて、お客様を絞り込むことが大事だと思っています。
だから当社は、企業ドメインを考えるときに、商品を絞り込むのではなくて、お客様を絞り込むことが大事だと思っています。
ーーー誰のために、を大切にしておられるのですね。競合他社が積極的に全国展開を行っている中で、御社はあえて関西を中心に地域を絞り込んで経営しておられるように思います。
寺西:はい、私共が大阪出身であることがスタートなのですが、私は薬局というビジネスは、ドミナント化(特定地域に集中すること)していかないといけないと思っています。
薬屋にとって大切なのが、認知度とか信頼性です。だから店舗同士の商圏をあえて被らせながら、どこに行ってもキリン堂がある状態を作っていきます。そうするとお客様理解が深まり、機能面でも利便性でも、常に地域の方に安心してもらえるブランドをつくることができます。
ぐっとインクが染み込むような点をたくさんつくりながら、大阪を中心に商圏を充足していき、その後、隣接した地域を第二商圏という形で、ドミナント化していく。最終的にはそれが全国に広がることになるかもしれませんが、それ以上に大事なことはドミナント化した中の1店1店が、地域のお客様に対して、店長さんの思いのこもった独自性のあるお店になることです。
薬屋にとって大切なのが、認知度とか信頼性です。だから店舗同士の商圏をあえて被らせながら、どこに行ってもキリン堂がある状態を作っていきます。そうするとお客様理解が深まり、機能面でも利便性でも、常に地域の方に安心してもらえるブランドをつくることができます。
ぐっとインクが染み込むような点をたくさんつくりながら、大阪を中心に商圏を充足していき、その後、隣接した地域を第二商圏という形で、ドミナント化していく。最終的にはそれが全国に広がることになるかもしれませんが、それ以上に大事なことはドミナント化した中の1店1店が、地域のお客様に対して、店長さんの思いのこもった独自性のあるお店になることです。
ーーー地域内でキリン堂の看板はたくさんありますが、それぞれのお店の中身はお客様のニーズによって変わるのですね。
寺西:はい。我々は個店経営と言ってるんですが、店舗が独自性を発揮できるよう、店長さんの成長を大切にしています。
店長さんが成長すると店が成長して、地域のお客さんへの貢献度が高まります。その総和が会社の成長です。会社があって店があるのではなく、はじめに店があって、それを支援するのが会社である。そういう考え方です。
店長さんが成長すると店が成長して、地域のお客さんへの貢献度が高まります。その総和が会社の成長です。会社があって店があるのではなく、はじめに店があって、それを支援するのが会社である。そういう考え方です。

地域のお客様像の解像度を上げる

ーーー実際、御社の人員構成を見ても、本部人員が少なく、小さい本部を志向されているように見えます。御社はなぜそのような「個店経営」を志向されているのでしょうか。
寺西:おっしゃる通りで私どもは小さな本部を目指しています。薬屋にとって大切なのが、地域のお客様1人1人に対するマーケティングです。
現代のお客様は、最大公約数的なサービスでは満足してもらえません。小さいエリアで細かくマーケティングしていかないと、売れるお店にはなりません。また、なまじ売れたとしても本当に我々が求めている「お客様貢献」は、実現できません。
例えば今、「健康フェア」といって血圧、骨密度、血管の弾力や、体脂肪といったあらゆる数値をバイタルチェックをしながら、お食事や健康食品の事をお伝えするイベントをそれぞれの店舗で推進しています。他にも育児相談会をやっているお店もありますし、そういうお店独自の取組みを増やしていきたいです。そういう取組を通して、キリン堂を中心にしたコミュニティができて、「なにも用事はないけど来たよ」と言ってもらえるようなお客様との関係性をつくりたい。ゆくゆくは、大丸さんとか高島屋さんと同じように「キリン堂さん」って親しみを込めて言っていただける小売店になりたいです。
現代のお客様は、最大公約数的なサービスでは満足してもらえません。小さいエリアで細かくマーケティングしていかないと、売れるお店にはなりません。また、なまじ売れたとしても本当に我々が求めている「お客様貢献」は、実現できません。
例えば今、「健康フェア」といって血圧、骨密度、血管の弾力や、体脂肪といったあらゆる数値をバイタルチェックをしながら、お食事や健康食品の事をお伝えするイベントをそれぞれの店舗で推進しています。他にも育児相談会をやっているお店もありますし、そういうお店独自の取組みを増やしていきたいです。そういう取組を通して、キリン堂を中心にしたコミュニティができて、「なにも用事はないけど来たよ」と言ってもらえるようなお客様との関係性をつくりたい。ゆくゆくは、大丸さんとか高島屋さんと同じように「キリン堂さん」って親しみを込めて言っていただける小売店になりたいです。
ーーードミナント化された出店で、地域のお客様像の解像度を上げて、どれだけ個別のサービスを提供できるかを大切にされているのですね。マニュアルベースの「それなりに品質が高い」画一的なサービスとは対極にある考え方ですね。そのような会社作りは寺西社長が社長の職につかれてからの変化だと思うのですが、お父様から社長職を引き継がれた時の会社の状況はどのようなものだったのでしょうか。
寺西:はい。私が社長に就任した時、すでに私たちには「未病」というコンセプトがあり、そのコンセプトに裏打ちされた営業力は、業界の中で定評がありました。
父が志した、病気になってからではなく、病気になる前に来ていただき、食事や生活習慣の改善で病気にならない体にしていこう、という「未病」に向かったお客様へのアプローチには、非常に強力なものだったのです。
ただ、そこに現場社員さんの意思はあまり入っていませんでした。上意下達的で、とにかく数売ったら褒められた。お客様が未病対策を実現できたかどうかは関係ありません。
私は、結果を出す土台になったそれぞれの社員さんの思いとか、考え方とか技術とか、そういうものを大切にしたいと思いました。「未病」の想いがない販売活動はお客様に伝わりません。売りこみのトークだけではない、マネージメント力や思考力をつけていきたいと思いました。
父が志した、病気になってからではなく、病気になる前に来ていただき、食事や生活習慣の改善で病気にならない体にしていこう、という「未病」に向かったお客様へのアプローチには、非常に強力なものだったのです。
ただ、そこに現場社員さんの意思はあまり入っていませんでした。上意下達的で、とにかく数売ったら褒められた。お客様が未病対策を実現できたかどうかは関係ありません。
私は、結果を出す土台になったそれぞれの社員さんの思いとか、考え方とか技術とか、そういうものを大切にしたいと思いました。「未病」の想いがない販売活動はお客様に伝わりません。売りこみのトークだけではない、マネージメント力や思考力をつけていきたいと思いました。

ーーー具体的にどのような場面でそういった事を感じられたのでしょう?
寺西:父の代と違い、時代は郊外型の大規模ドラッグストアを求めるようになってきました。ドラッグストアとしてお客様に来店いただけなければ未病のコンセプトは実現しません。ですから我々もそういった形態の店舗展開に乗り出したんですが、社員さんがついてこない。
例えば、大型店では品出しの作業量が大きく膨らむのですが、考え方の転換ができず、多くの店で品出しが不十分なままに販売を行っていました。
便利で、安い買い物してもらい、来店頻度を高めたい、というコンセプトに対して、社員さんは「こんな業務するためにキリン堂に入ってきたわけではない、私は売りたいんや」そう考えていました。未病対策と大型化のつながりが理解してもらえていなかったのかもしれません。
オペレーションが身につかず、地につかない事業が続きました。効率よくオペレーションしたいのにできない。もどかしく、すごくしんどかったですね。
例えば、大型店では品出しの作業量が大きく膨らむのですが、考え方の転換ができず、多くの店で品出しが不十分なままに販売を行っていました。
便利で、安い買い物してもらい、来店頻度を高めたい、というコンセプトに対して、社員さんは「こんな業務するためにキリン堂に入ってきたわけではない、私は売りたいんや」そう考えていました。未病対策と大型化のつながりが理解してもらえていなかったのかもしれません。
オペレーションが身につかず、地につかない事業が続きました。効率よくオペレーションしたいのにできない。もどかしく、すごくしんどかったですね。
ーーーどのように乗り越えられたんですか?
寺西:お客様をたくさん呼びました。
私は人の「理解」には3つの種類があると思います。心の理解、頭の理解、それから体の理解です。一番大事なのは体の理解です。私たち小売業に携わる者は、やっぱりお客様がたくさん来て、たくさん買っていただくことが心底嬉しい。
お店にたくさんのお客様を呼ぶと、自然と品出しできていないことやそれ故に接客が十分にできないことが目に付くようになります。そうやってお客様を呼んで店舗が忙しくなることで大切な事が何なのか、社員さんが体で理解していきました。
そうやって、たくさんお客様に満足いただけるような業務をすると、更に接客の機会が増える。そうするとまた業務が改善される。そういう良循環をつくることで、社員さんがだんだん賛同してくれるようになりました。
私は人の「理解」には3つの種類があると思います。心の理解、頭の理解、それから体の理解です。一番大事なのは体の理解です。私たち小売業に携わる者は、やっぱりお客様がたくさん来て、たくさん買っていただくことが心底嬉しい。
お店にたくさんのお客様を呼ぶと、自然と品出しできていないことやそれ故に接客が十分にできないことが目に付くようになります。そうやってお客様を呼んで店舗が忙しくなることで大切な事が何なのか、社員さんが体で理解していきました。
そうやって、たくさんお客様に満足いただけるような業務をすると、更に接客の機会が増える。そうするとまた業務が改善される。そういう良循環をつくることで、社員さんがだんだん賛同してくれるようになりました。

大事だから頑張るというより、頑張ったから大事になる

ーーーオペレーションが出発点なのではなくてお客様をたくさん呼ぶっていうことを出発点にされたんですね。どうやってお客様を増やしたのですか。
寺西:広告やイベント、店舗形態など色々ありますが、共通点は「真似」ですね。例えばドラッグストアの店舗形態で言えば、関東が先進地域なんです。それを見に行っては愚直に真似して、うまくいかなかったところは変えて、トライアンドエラーを繰り返しました。
ーーーまずは「真似」から始められたのですね。そうやってお客様が増えて、満足にサービスができなくなってきたから工夫せざるをえない状況になる。理屈を説くより体を動かすことを大切にしておられるのですね。
寺西:心が変わったから、体が動いた、というのもあると思いますが、やっぱり我々実務家なので。まずは体で理解することが大事だと思いますね。
ーーーいや、おっしゃる通りですね。大事だから頑張るというより、頑張ったから大事になるっていうことの方がリアルな気がします。現在御社は、美容の分野にも進出されていますね。
寺西:元々、薬屋というのはヘルス&ビューティということで、化粧品と薬を販売する形態が業界ではオーソドックスなんですが、当社はヘルスを中心にしてビューティ部門は細々とやっていたんです。
しかし、郊外型の大規模ドラッグストアとなると、お客様からのニーズに応えるためにも、ビューティ部門はなくてはなりません。そこで、ただ他のお店と同じ化粧品を扱うだけでなく、「内面美容」を大切にしたビューティ部門をつくろうということになったのです。つまり体の中から綺麗になってもらう、という価値を提供しよう、ということです。
今まで得意としてきた健康食品もありますし、扱う化粧品もノンケミカルで自分の肌の力を引き出すような商品をプライベートブランドでつくっていくことにしました。プライベートブランドの化粧品は、美容部員の方の意見や、お客様の意見を伺いながら商品化しています。公的ではないですが、社内資格もあります。化粧品メーカーさんと一緒になって知識の習得に励んでいます。
しかし、郊外型の大規模ドラッグストアとなると、お客様からのニーズに応えるためにも、ビューティ部門はなくてはなりません。そこで、ただ他のお店と同じ化粧品を扱うだけでなく、「内面美容」を大切にしたビューティ部門をつくろうということになったのです。つまり体の中から綺麗になってもらう、という価値を提供しよう、ということです。
今まで得意としてきた健康食品もありますし、扱う化粧品もノンケミカルで自分の肌の力を引き出すような商品をプライベートブランドでつくっていくことにしました。プライベートブランドの化粧品は、美容部員の方の意見や、お客様の意見を伺いながら商品化しています。公的ではないですが、社内資格もあります。化粧品メーカーさんと一緒になって知識の習得に励んでいます。

私が考える現場力教育とは

ーーーなるほど、「未病」のコンセプトにも通じる取組みですね。最近は生鮮商品の販売にもチャレンジしておられます。
寺西:はい、これは他社でも力を入れている取組ですが、お客様の来店頻度を高めるために販売に取り組んでいます。
ご来店いただき、お客さんとの接点を増やすことで、ヘルス&ビューティ分野で様々な気づきを得ていただけると思っています。また、そういった事を通じて、食を含めたお一人お一人のお客様のウォレットシェア(顧客内シェア)を高めていきたいと思っています。
ご来店いただき、お客さんとの接点を増やすことで、ヘルス&ビューティ分野で様々な気づきを得ていただけると思っています。また、そういった事を通じて、食を含めたお一人お一人のお客様のウォレットシェア(顧客内シェア)を高めていきたいと思っています。
ーーーお客様のウォレットシェアを上げるために大事なことは何でしょう?
寺西:喜んでいただくことにつきます。価格、価値、品揃えの3つが重要です。リーズナブルであることは大切ですが、安いだけではお客様に価値を感じていただけることはできません。
価値ある商品を妥当な価格で提供することが重要です。また同時に品揃えも大切です。多くのメーカーさん、ベンダーさんとお付き合いして商品ラインナップを拡充しています。
価値ある商品を妥当な価格で提供することが重要です。また同時に品揃えも大切です。多くのメーカーさん、ベンダーさんとお付き合いして商品ラインナップを拡充しています。
ーーー回転が速い生鮮品を商品ラインナップに加えると、品出し等、現場の皆さんの仕事量は飛躍的に多くなったのでしょうね。
寺西:今は分業化してパートさんやアルバイトさんがしている仕事も最初は何から何まで社員が作業していたので、はじめは反発があったと思います。でも会社が腹を決めてやり出したからにはやりきらない選択肢はありません。しばらくするとみんな一生懸命やってくれるようになりました。
ーーーこういう変革をやり切るためには、経営陣の意志は勿論、現場力も大事な要素だと思います。
寺西:はい。小売業なので、人が一番大事な要素です。当社が大きく成長した高度成長期の時代は、上司が決めたことをいかに徹底させるか、ということが人材育成の中で一番大事な事でした。
確かにそれで販売力は上がるのですが、それでは業界の変化や、お客様ニーズの多様化には対応できません。仕事を自分の人生の一部だと思っていただけるような人を育てることが大切です。そういうことが人間の成長だと考えたら、上司が決めたことを徹底することでは、人を成長させることはできません。
教育制度、組織、いろいろな形をつくって、社員に成長してもらい、また幸福になってもらうこと。お客様貢献や患者様の回復を心から願うことができる社員さんをつくることが私の考える現場力教育です。近年はそういう社員が増えてきた、という実感があります。
確かにそれで販売力は上がるのですが、それでは業界の変化や、お客様ニーズの多様化には対応できません。仕事を自分の人生の一部だと思っていただけるような人を育てることが大切です。そういうことが人間の成長だと考えたら、上司が決めたことを徹底することでは、人を成長させることはできません。
教育制度、組織、いろいろな形をつくって、社員に成長してもらい、また幸福になってもらうこと。お客様貢献や患者様の回復を心から願うことができる社員さんをつくることが私の考える現場力教育です。近年はそういう社員が増えてきた、という実感があります。

マスの経済理論だけが正義というわけではない

ーーー仕事の目的を自分の人生の目的と重ねられるような社員さんの育成を目指しておられるのですね。非常に本質的で非常に足の長い取り組みですね。ところで昨年、御社の上場廃止がニュースになりました。差し支えなければ経緯を教えていただけますか?
寺西:私たちが最初に株式上場を志したのはまだ売り上げが100億にも届かない1980年代でした。野村證券出身の専務が来て、「薬局の社会的ステータスを上げ、今以上の成長を目指した資本政策のために上場を目指そう」、と全社を先導してくれて15年かかって上場することができました。
しかし実際に上場をしていると、クオーター単位で目の前の数字をつくっていく必要があり、なかなか本質的なことに着手できません。数字を作る根源には、人の成長があります。会社としては、社会から預かった人を1人前にしなければいけません。
そういう仕事をおろそかにするわけにはいきません。そういう経緯でMBO(経営者の自社株買取)を決断しました。
しかし実際に上場をしていると、クオーター単位で目の前の数字をつくっていく必要があり、なかなか本質的なことに着手できません。数字を作る根源には、人の成長があります。会社としては、社会から預かった人を1人前にしなければいけません。
そういう仕事をおろそかにするわけにはいきません。そういう経緯でMBO(経営者の自社株買取)を決断しました。
ーーー莫大な資金も必要ですし、大変なご決断だったと思うのですが、具体的な問題意識はどこにあったのでしょう。
寺西:このままではいけないという危機感が強くありました。全国内の順位は11位、業界は合従連衡が進んでいました。
しかし、自分たちの手で価値を創造していきたいし、自分たちの頭でお客さん貢献を作っていきたい。マスの経済理論だけが正義というわけではない。そう思いました。
現在はライバルに比べて、収益性も少し見劣りするし、規模も小さいキリン堂ですが、今回の上場廃止を通じて、筋肉質の体質をつくってさらなる成長を果たしたいと思っています。
しかし、自分たちの手で価値を創造していきたいし、自分たちの頭でお客さん貢献を作っていきたい。マスの経済理論だけが正義というわけではない。そう思いました。
現在はライバルに比べて、収益性も少し見劣りするし、規模も小さいキリン堂ですが、今回の上場廃止を通じて、筋肉質の体質をつくってさらなる成長を果たしたいと思っています。
ーーー非常に切迫した危機意識があったのですね。
寺西:当時の延長線上で仕事をしていたら、成果さえあげたらいいという価値観から抜け出すことはできませんでした。
いい会社の根本は人の力です。様々な技術革新やマーケティング手法も取り入れるのですが、それを動かす土台は長期的な視点で育成された人間だと思っています。地場のお客様に喜んでもらえる会社はそのようにしてつくられる、と信じています。
いい会社の根本は人の力です。様々な技術革新やマーケティング手法も取り入れるのですが、それを動かす土台は長期的な視点で育成された人間だと思っています。地場のお客様に喜んでもらえる会社はそのようにしてつくられる、と信じています。
ーーー体質改善というと、リストラを通じて無駄なコストを減らすことが思い起こされますが、御社はそうではなかったんですね。人材育成は果てしない取組みですが、一番大事なことは「人材を育成しようと本気で思う」ことだと思います。
寺西:はい、その通りですね。
キリン堂の皆さんは真面目できっちり仕事してくれるのですが、自分で考えて提案したりするのが苦手だったと思います。地場のお客様に喜んでもらうには、もっと考える社員さんが育っていないといけない。
上場廃止をして、成果だけに追われない環境をつくることができたからこそ、腰を据えて人材育成にチャレンジすることができます。
キリン堂の皆さんは真面目できっちり仕事してくれるのですが、自分で考えて提案したりするのが苦手だったと思います。地場のお客様に喜んでもらうには、もっと考える社員さんが育っていないといけない。
上場廃止をして、成果だけに追われない環境をつくることができたからこそ、腰を据えて人材育成にチャレンジすることができます。
ーーー非常に意志が強い決定ですよね。
寺西:とにかくとどまっておれないことだけは確かなんです。業界は合従連携の流れですし、その方が効率は上がりますが、やっぱりキリン堂のならではの、お客様に寄り添って未病対策を実現する、という理念を、人間の力で実現していきたいのです。
1人1人のお客さんと接する時には、1対1です。資本が大きいからその話を聞いてくれるわけではありません。それが事実です。事実に基づいて考えると競争力の源泉は資本の大きさではない。人です。
力つけていくためには資本も必要ですが、それ以上に大事なことは、組織の理念と人の力です。現地現物で考えれば、それは明らかなことです。
1人1人のお客さんと接する時には、1対1です。資本が大きいからその話を聞いてくれるわけではありません。それが事実です。事実に基づいて考えると競争力の源泉は資本の大きさではない。人です。
力つけていくためには資本も必要ですが、それ以上に大事なことは、組織の理念と人の力です。現地現物で考えれば、それは明らかなことです。

私自身が、空気を作る

ーーー競争力の源泉はお客様に向き合う力ということですが、それを高める上で大切にされていることは何ですか?
寺西:任せることです。任せることで初めて、社員さんが自分で考える土壌ができます。イメージとしては、社長が一番下にいて、お客様、お店が一番上にある組織です。
社長も部長も、店長も、任される場所は違いますが、同じ任されたという意味では同じです。すべての社員さんに、自分の人生の一部として仕事に取り組んでもらいたいです。
その為には、信頼し合うことがとても大切です。信頼感で結ばれたチームを作るためには、社員さんが自ら学び、自ら力をもつけることが不可欠です。信頼感は隷属的なチームには必要ありませんが、任せるチームをつくるには不可欠な要素です。
社長も部長も、店長も、任される場所は違いますが、同じ任されたという意味では同じです。すべての社員さんに、自分の人生の一部として仕事に取り組んでもらいたいです。
その為には、信頼し合うことがとても大切です。信頼感で結ばれたチームを作るためには、社員さんが自ら学び、自ら力をもつけることが不可欠です。信頼感は隷属的なチームには必要ありませんが、任せるチームをつくるには不可欠な要素です。
ーーー信頼感を高めるために、社長はどのようなことを意識しておられますか。
寺西:まず私自身が、空気を作ることです。勉強して、成長を喜びとすること。もっと良くしたい、もっと改善したいという気持ちで仕事に当たること。それに何か感じた人が火種になって、また新しい火をつけてくれます。職場の活気ってそういう地道な事でつくられていくのだと思います。
ーーー小売業は長らく、オペレーションを商売の最重要項目にしてきたと思います。今、固定的なオペレーション以上に社員の成長を志しておられる理由は何でしょう?
寺西:これからの時代、反復作業はすべて機械の仕事に置き変わっていきます。人間の仕事は、そこに人が存在する価値が見出せなくてはいけません。お客さん状況をお伺いして提案すること、「この間の薬、効いたで!」というお客様の喜びを我がことのように聴くこと。そういうことが、人間がそこにいる価値だと思います。
我々は健康や健康ゆえに楽しめる家族の団らんそのものを売り物にしています。そういうものを、お客様に提供しようと思ったら、お客様に寄り添う社員の成長が必要なんです。機能だけではない、感情が動く、そういう場所にこそ人が介在する価値があるんじゃないでしょうか。
我々は健康や健康ゆえに楽しめる家族の団らんそのものを売り物にしています。そういうものを、お客様に提供しようと思ったら、お客様に寄り添う社員の成長が必要なんです。機能だけではない、感情が動く、そういう場所にこそ人が介在する価値があるんじゃないでしょうか。

ーーーAmazonGoみたいなお店ばかりになれば、それこそネットで注文したらいいって世界になってしまいますね。
寺西:とどのつまり、機能だけならネットのほうが優秀なんですよね。私たちは機能の外側にこそお客さんのニーズがあると思っています。信頼できる人から薬を買いたい、というお客様の思いは、機能だけでは説明できないものです。
もしそこに人の力や人の価値がなくなってしまったら、薬局はただのショールームとして使われて購入はネットで、ということになってしまいます。人の成長が全てです。
もしそこに人の力や人の価値がなくなってしまったら、薬局はただのショールームとして使われて購入はネットで、ということになってしまいます。人の成長が全てです。
ーーー最後に、御社の今後目指す姿を教えてください。
寺西:尊敬される会社になりたいです。当社では「アドマイヤードカンパニー」って言っています。
その為に、まずは店長さんが一人の人間として、地域の中で尊敬されないといけない。銀行さんの支店長と同じように「キリン堂の店長だ」って胸を張ってもらいたい。その源泉はお客様からの信頼です。
だから当面当社の目指すところは、関西でナンバーワンのサービスができる会社です。ナンバーワンのお客さんの喜びを生み出して、結果として関西で売上高ナンバーワンの会社になりたいです。
近い未来では再上場。再上場するということは、我々が筋肉質になって生まれ変わったということの証明です。どれぐらい短期間でこれが実現できるか、時間との闘いだと思っています。
その為に、まずは店長さんが一人の人間として、地域の中で尊敬されないといけない。銀行さんの支店長と同じように「キリン堂の店長だ」って胸を張ってもらいたい。その源泉はお客様からの信頼です。
だから当面当社の目指すところは、関西でナンバーワンのサービスができる会社です。ナンバーワンのお客さんの喜びを生み出して、結果として関西で売上高ナンバーワンの会社になりたいです。
近い未来では再上場。再上場するということは、我々が筋肉質になって生まれ変わったということの証明です。どれぐらい短期間でこれが実現できるか、時間との闘いだと思っています。
ーーー人材育成の成果が筋肉、ですね。果てしないビジョンのもとに努力する中で苦しみはありませんか。
寺西:毎日が苦しいです。ただ同じぐらい楽しんで仕事させてもらっています。
創業の頃は九州や四国で苦労して採用活動をしてなんとか入社してもらっていました。仕事も雨が降ったら会社に来てくれないとかそんな状況で。だから今、会社の形が整ってきて、社員の皆さん少しずつイキイキ仕事できるようになってきたのが本当にありがたい。そういう感謝を常に感じています。だから苦しいなんて言ってられません。
創業の頃は九州や四国で苦労して採用活動をしてなんとか入社してもらっていました。仕事も雨が降ったら会社に来てくれないとかそんな状況で。だから今、会社の形が整ってきて、社員の皆さん少しずつイキイキ仕事できるようになってきたのが本当にありがたい。そういう感謝を常に感じています。だから苦しいなんて言ってられません。
ーーー社長の想いに非常に共感します。私たちの会社はまだ御社の歩んでこられた道のずっと手前にいると思うのですが、当社のメンバーに対してメッセージ一言でいただけますか。
寺西:車はすごく夢がある商品です。カーライフと言われるように、家族の団らんを支え、豊かで楽しい生活の基盤になるのが車という商品です。
そういう生活に思いを馳せ、自分で考えて仕事をしていただく事がそれぞれの社員の皆様と会社の成長と幸せにつながるのではないか、と思っています。お互い頑張りましょう。
そういう生活に思いを馳せ、自分で考えて仕事をしていただく事がそれぞれの社員の皆様と会社の成長と幸せにつながるのではないか、と思っています。お互い頑張りましょう。
ーーー本日は貴重な機会をありがとうございました。

株式会社キリン堂
〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36
聞き手:小西敏仁 / 撮影・構成:山本一夫(広報室)
私たちネッツトヨタニューリー北大阪株式会社は1961年の創業以来、 「自分の子供を入れたくなる会社になる」「世代を超えて100年続く」という2つのゴールを掲げ、社員にとって幸せな職場になることを一貫して目指してまいりました。 このコーナーでは従業員を大切に経営されている企業トップにインタビューさせていただき、社員価値の高い企業づくりについて学びます。 真のお客様価値は幸せに働く社員によって生み出される、が私たちの信念です。記事を通して私たちの目指すゴールを多くの方に知って頂ければ幸いです。
ネッツトヨタニューリー北大阪株式会社
代表取締役社長 小西 敏仁