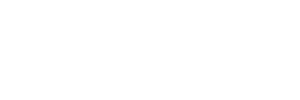【番外編】豊中市社会福祉協議会 勝部麗子さん(後編)
※このインタビューは、[前編]の続きです
第2回トップインタビューの㈱プロアシストの木下社長のお話の中で、孤独死の壮絶な現場について知りました。以来ずっと、私たちの生活のすぐ隣で孤独死が起こっているという事実がずっと心に引っかかっていました。考えていくうち、一人で亡くなる方がいることが問題なのではなく、亡くなってから何週間も周りの人に気づいてもらえないぐらい社会的に孤立していることが問題なのだと考えるようになりました。私たちにできることは何なのか。考えていく中で、豊中の社会福祉協議会に社会的孤立と戦う女性がいると伺いました。日本のコミュニティーソーシャルワーカーのトップランナー、勝部麗子さんです。コミュニティーソーシャルワーカーの生みの親でもある勝部さん、その活動は、自身をモデルにしたNHKドラマ『サイレント・プア』や『プロフェッショナル 仕事の流儀』で日本中に広く知られています。社会的な孤立を防ぐために、私たちにできることは何なのか。勝部さんにお話しを伺いました。
第2回トップインタビューの㈱プロアシストの木下社長のお話の中で、孤独死の壮絶な現場について知りました。以来ずっと、私たちの生活のすぐ隣で孤独死が起こっているという事実がずっと心に引っかかっていました。考えていくうち、一人で亡くなる方がいることが問題なのではなく、亡くなってから何週間も周りの人に気づいてもらえないぐらい社会的に孤立していることが問題なのだと考えるようになりました。私たちにできることは何なのか。考えていく中で、豊中の社会福祉協議会に社会的孤立と戦う女性がいると伺いました。日本のコミュニティーソーシャルワーカーのトップランナー、勝部麗子さんです。コミュニティーソーシャルワーカーの生みの親でもある勝部さん、その活動は、自身をモデルにしたNHKドラマ『サイレント・プア』や『プロフェッショナル 仕事の流儀』で日本中に広く知られています。社会的な孤立を防ぐために、私たちにできることは何なのか。勝部さんにお話しを伺いました。


役割づくり
インタビューの途中、勝部さんは室外の男性に気づかれて、慌てて離席されました。部屋に戻ってきた勝部さんは、男性との驚くべきエピソードを教えてくださったのです。
******
勝部:彼は50代なのですが、かれこれ30年も家から出ることができない引きこもりだったんですよ。
見守りをしていただいているご近所の方からの心配の声を受けて尋ねたのが出会いです。30年間ずっと外に出ていないそうで、髪の毛も自分で切っていたのでボサボサ。すごい状態でした。色々話すと「働きたいけどもう30年も働いていないからどうにもならない」って。
元々、メンタル的に問題があった上に、親子関係が悪くなり、だんだん苦しくなって外へ出る自信を失っていったそうです。働きたい思いはあっても、どこに相談に行っていいかもわからない孤立した状況だったそうです。自分一人ではどうしようもない。それが彼の思いでした。
それでまずは、社会福祉協議会に散髪ボラティアさんをお呼びして散髪をすることにしたんです。移動手段がない彼の為に、豊中市の環境部がリユースしている、廃棄自転車も準備しました。
見守りをしていただいているご近所の方からの心配の声を受けて尋ねたのが出会いです。30年間ずっと外に出ていないそうで、髪の毛も自分で切っていたのでボサボサ。すごい状態でした。色々話すと「働きたいけどもう30年も働いていないからどうにもならない」って。
元々、メンタル的に問題があった上に、親子関係が悪くなり、だんだん苦しくなって外へ出る自信を失っていったそうです。働きたい思いはあっても、どこに相談に行っていいかもわからない孤立した状況だったそうです。自分一人ではどうしようもない。それが彼の思いでした。
それでまずは、社会福祉協議会に散髪ボラティアさんをお呼びして散髪をすることにしたんです。移動手段がない彼の為に、豊中市の環境部がリユースしている、廃棄自転車も準備しました。

──外に出て、髪を切る。外の社会とつながる大きなきっかけですね。
勝部:はい、そうしたら仕事をしたいってことで、今、彼の就労支援を始めることになったんです。自転車に乗って髪を切りに行くことで、彼の人生が大きく変わったと思います。
彼と初めて会ったのがつい2か月前です。私たちが訪問して、一緒に歩いてくれる人が見つかったということが大きなきっかけになったと思います。
彼と初めて会ったのがつい2か月前です。私たちが訪問して、一緒に歩いてくれる人が見つかったということが大きなきっかけになったと思います。
──気にしてくれる人がいることで、大きな勇気が生まれるのですね。
勝部:30年ぐらいずっと家の中から出てない彼が、さっきはすごく明るい表情で仕事がしたいと話してくれたんです。もう泣きそうになりました。
人は、誰かと一緒だったら変わっていけるのです。その誰かは家族であるケースも多いですが、親子関係が苦しくなっている人には、第三者の介入が必要です。そういう関わりを、豊中に18人いる我々ソーシャルワーカーは目指しています。
さっきの彼は最初の訪問を通じて大きく変わりましたが、54回通いつづけてやっと繋がれた人もいるんです。
人は、誰かと一緒だったら変わっていけるのです。その誰かは家族であるケースも多いですが、親子関係が苦しくなっている人には、第三者の介入が必要です。そういう関わりを、豊中に18人いる我々ソーシャルワーカーは目指しています。
さっきの彼は最初の訪問を通じて大きく変わりましたが、54回通いつづけてやっと繋がれた人もいるんです。

──会えない中で、54回も通われたんですか。すごいエネルギーですね!
勝部:一人を助けるのにそんなに沢山のエネルギーを使っていたらキリがない、とよく言われます。
でもそういう人の後ろには、同じような状況に苦しんでいる人が沢山いるのです。現場に行って、その人を助けるためにいろんな課題をひとつひとつ潰していくと、同じような状況にいる人たちを救うための普遍的な方法が見えてきます。
例えば引きこもりの若者は、家から出たくなくて引きこもっている訳じゃないんですよ。「行く場がない」というのが引きこもり問題の本質だと思います。だから、行ける場所と理由を作ってあげればいい。
私たちは、彼らがどうやったら外に出てきてくれるだろうって考えて、小さなアルバイトを提供する場所を作ってみました。そうすると、自分のお小遣いになるんだったら出てみようかなという気持ちになって、外に出る理由ができました。そうやって家から出てきた若者が200人もいるんです。これは一人に真剣に向き合ったからこそ見つけられたやり方なんです。
豊中は高学歴の引きこもりの子どもも多くて、対人関係は苦手だけど、一部の事はすごく上手くできる子どもが多いんです。どういう仕事だったら、本人たちがプライドを持ってできるのか考えて、プログラミングの会社と提携して、彼らの能力を引き出せるようなものができないか企画したりしています。
また、絵が得意な子もいたので、じゃあ漫画で社会福祉協議会の活動を紹介してよと依頼して、私たちの活動を漫画にしてもらったりしました。私たちの活動を紹介した漫画は全部で5巻あるのですが、ひきこもりとかゴミ屋敷とか引きこもりなどいろんなパターンの漫画を出しているのですが、これがNHKドラマ部の目に止まり、これが『サイレントプア』というドラマになったんです。
でもそういう人の後ろには、同じような状況に苦しんでいる人が沢山いるのです。現場に行って、その人を助けるためにいろんな課題をひとつひとつ潰していくと、同じような状況にいる人たちを救うための普遍的な方法が見えてきます。
例えば引きこもりの若者は、家から出たくなくて引きこもっている訳じゃないんですよ。「行く場がない」というのが引きこもり問題の本質だと思います。だから、行ける場所と理由を作ってあげればいい。
私たちは、彼らがどうやったら外に出てきてくれるだろうって考えて、小さなアルバイトを提供する場所を作ってみました。そうすると、自分のお小遣いになるんだったら出てみようかなという気持ちになって、外に出る理由ができました。そうやって家から出てきた若者が200人もいるんです。これは一人に真剣に向き合ったからこそ見つけられたやり方なんです。
豊中は高学歴の引きこもりの子どもも多くて、対人関係は苦手だけど、一部の事はすごく上手くできる子どもが多いんです。どういう仕事だったら、本人たちがプライドを持ってできるのか考えて、プログラミングの会社と提携して、彼らの能力を引き出せるようなものができないか企画したりしています。
また、絵が得意な子もいたので、じゃあ漫画で社会福祉協議会の活動を紹介してよと依頼して、私たちの活動を漫画にしてもらったりしました。私たちの活動を紹介した漫画は全部で5巻あるのですが、ひきこもりとかゴミ屋敷とか引きこもりなどいろんなパターンの漫画を出しているのですが、これがNHKドラマ部の目に止まり、これが『サイレントプア』というドラマになったんです。

──メディアに取り上げられるきっかけになったドラマですね。
勝部:そうなんです。漫画ってコマ割りがあって構成しやすいからなのか、ドラマ化されるものが多いんです。
私の役は深田恭子さんが演じられたんですが、美しすぎて、実際にそんな人いないでしょって(笑)。そういう仕事に取り組んでいる人が本当にいることを世の中に示したい、という企画が立ち上がり『プロフェッショナル仕事の流儀』に出演することになり、ゴミ屋敷の片づけや、孤独死に遭遇して場面を紹介いただきました。
私の役は深田恭子さんが演じられたんですが、美しすぎて、実際にそんな人いないでしょって(笑)。そういう仕事に取り組んでいる人が本当にいることを世の中に示したい、という企画が立ち上がり『プロフェッショナル仕事の流儀』に出演することになり、ゴミ屋敷の片づけや、孤独死に遭遇して場面を紹介いただきました。

──役割を作るというのは、人を孤独にしない大きな解決策ですね。
勝部:まさにその通りです。「すべての人に居場所と役割を作る」ことが、私の活動のテーマです。
今、定年後の男性の皆さんと一緒に、都市型農園「豊中あぐり」という活動を行っています。農業を通じて定年後の皆さんと社会のつながりを作ることが目的です。最近は野菜をつくるだけじゃなくて、農業を通じて児童養護施設の子供たちと交流しています。スイカが丸いことを知らなかった子どもがいていたりねぇ・・そういうことが子供たちのいろんな情操教育に協力できている思うと、参加しているみんなは嬉しいじゃないですか。いくつになっても人には必ず役割があるんです。
でも今の世の中、どう生きればいいのか見出せなくなっていってる人たちがたくさんいます。ボランティア活動の本質って特別なことではなくて、「その人の役割を引き出す」ことだと思います。引きこもっていた若者たちは今、電球交換や大型ゴミ出しをしに高齢者のところに行ってくれています。
これ、「絵が描ける引きこもりの人はいいわよね。うちの息子は絵も描けないわ」ってお母さんに言われて「いえいえ、府営住宅でゴミが出せないおばあちゃんより若いじゃないですか!」って言い返したことがきっかけなんです。
ああ、こんなことで人から喜ばれるんだ、と思うと同時に、人の役に立つことで自分が満たされていく実感が本人たちにあるのだと思います。そこから自己肯定感が湧いてくるのだと思います。必要とされていない人は誰ひとりいないのです。
誰からも必要とされていないと思っている方がたくさんここに相談に来られます。でもそんな方々は、コロナ禍で自分も減収で大変なのに子供食堂に寄付してくださる方だったり、残った食品ロスのものを届けてくださる方だったり、自分ができることに協力していただける方だったりします。
そういうことを通じて、今度は自分に難しいことがあったら助けてもらう、そんな繋がりができてきます。そういう繋がりの作り手として私たちはいるのかなって思っています。
今、定年後の男性の皆さんと一緒に、都市型農園「豊中あぐり」という活動を行っています。農業を通じて定年後の皆さんと社会のつながりを作ることが目的です。最近は野菜をつくるだけじゃなくて、農業を通じて児童養護施設の子供たちと交流しています。スイカが丸いことを知らなかった子どもがいていたりねぇ・・そういうことが子供たちのいろんな情操教育に協力できている思うと、参加しているみんなは嬉しいじゃないですか。いくつになっても人には必ず役割があるんです。
でも今の世の中、どう生きればいいのか見出せなくなっていってる人たちがたくさんいます。ボランティア活動の本質って特別なことではなくて、「その人の役割を引き出す」ことだと思います。引きこもっていた若者たちは今、電球交換や大型ゴミ出しをしに高齢者のところに行ってくれています。
これ、「絵が描ける引きこもりの人はいいわよね。うちの息子は絵も描けないわ」ってお母さんに言われて「いえいえ、府営住宅でゴミが出せないおばあちゃんより若いじゃないですか!」って言い返したことがきっかけなんです。
ああ、こんなことで人から喜ばれるんだ、と思うと同時に、人の役に立つことで自分が満たされていく実感が本人たちにあるのだと思います。そこから自己肯定感が湧いてくるのだと思います。必要とされていない人は誰ひとりいないのです。
誰からも必要とされていないと思っている方がたくさんここに相談に来られます。でもそんな方々は、コロナ禍で自分も減収で大変なのに子供食堂に寄付してくださる方だったり、残った食品ロスのものを届けてくださる方だったり、自分ができることに協力していただける方だったりします。
そういうことを通じて、今度は自分に難しいことがあったら助けてもらう、そんな繋がりができてきます。そういう繋がりの作り手として私たちはいるのかなって思っています。
──私たち現役世代は「役割があって当たり前」の世界に生きていますが、勝部さんのお話に触れるだけで、ちょっと気持ちが変わりますね。
勝部:働くことでもっと周りの人を元気にできることがいろいろあるはずなので、企業がお仕事をちょっとシェアしてくれることで、多くの人たちをサポートできるようになります。これからは高齢化社会ですから、第2第3のお仕事を作ってあげないとみんな生きていけないですからね。高齢者が、いろいろな役割が持てるような仕事が増えていくといいな、と思っています。
私は独居死と孤独死は違うと思っています。一人暮らしでも誰かとの繋がりがあれば人って元気になっていきます。でも、誰かと喋りたいと思っても誰もいないとか、誰からも必要とされてないと思える状況は人をどんどん弱らせていきます。そんな「望まない孤独」が孤独死を生むのです。だから、すべての人に居場所と役割を考えていきたいです
私は独居死と孤独死は違うと思っています。一人暮らしでも誰かとの繋がりがあれば人って元気になっていきます。でも、誰かと喋りたいと思っても誰もいないとか、誰からも必要とされてないと思える状況は人をどんどん弱らせていきます。そんな「望まない孤独」が孤独死を生むのです。だから、すべての人に居場所と役割を考えていきたいです

優しい地域を作る

──活動していく中で、嬉しい瞬間って、どんな時ですか
勝部:嬉しい瞬間はたくさんありますよ。さっきみたいに引きこもりの子が変わっていく瞬間なんかはもちろん嬉しいんですし。豊中あぐりの活動なんて、「最初は野菜作りなんか、と思っていたけど、豊中あぐりがあってよかった。妻が死んで独りになって、近所に誰も友達おらんかったから。」って言われたり。
でもそれ以上に「あの人がこんな風に変わったんだよ」って、地域の人たちが自分事のように嬉しそうに喋っておられるときが一番嬉しいですね。
昔の豊中はこんな優しい街じゃありませんでした。例えば昔なら、公園にホームレスの人がいたら「早く公園から出してください、子どもが危ない」という電話があったものですが、今は「心配だから助けてあげてほしい」って言われるんです。
こういう街になってとても嬉しいなと思うんです。これがコロナによってすべて活動停止になったんですよ。集まったらダメ、一緒にご飯食べたらダメ、サロンでみんなでお茶飲んだらダメ、子供食堂でご飯作ってあげるのもダメ。全部ダメになってしまったこの2年は、私たちは今までやってきた手法が全部もぎ取られたような感じでした。
でもそれ以上に「あの人がこんな風に変わったんだよ」って、地域の人たちが自分事のように嬉しそうに喋っておられるときが一番嬉しいですね。
昔の豊中はこんな優しい街じゃありませんでした。例えば昔なら、公園にホームレスの人がいたら「早く公園から出してください、子どもが危ない」という電話があったものですが、今は「心配だから助けてあげてほしい」って言われるんです。
こういう街になってとても嬉しいなと思うんです。これがコロナによってすべて活動停止になったんですよ。集まったらダメ、一緒にご飯食べたらダメ、サロンでみんなでお茶飲んだらダメ、子供食堂でご飯作ってあげるのもダメ。全部ダメになってしまったこの2年は、私たちは今までやってきた手法が全部もぎ取られたような感じでした。
──人と人が直接会うことが大きく制限されています。
勝部:全てのことができなくなりました。
そしたら起こったことは、孤独死なんです。人って、繋がりがなくなったら死んでいくんです。今までみたいに毎月集まっていた時だったら、助けてあげられたのに。そう思うのは本当に悔しいです。
ボランティアの人から「勝部さん、『孤独を作ったらあかん!見守りしなきゃ!』なんて言いまくってたのに、コロナが起きたからって、すべてお休みでいいの!?」って叱られたんです。私が、感染症が広がったらダメだ、そればっかり思ってた時です。今考えれば嬉しい話ですよね。そんなことで止めてる場合じゃない。感染拡大に留意しながら少しずつ活動再開しています。
自分たちの街で他の人が幸せになっていくことを喜ぶ人たちいることがすごく嬉しいです。
そしたら起こったことは、孤独死なんです。人って、繋がりがなくなったら死んでいくんです。今までみたいに毎月集まっていた時だったら、助けてあげられたのに。そう思うのは本当に悔しいです。
ボランティアの人から「勝部さん、『孤独を作ったらあかん!見守りしなきゃ!』なんて言いまくってたのに、コロナが起きたからって、すべてお休みでいいの!?」って叱られたんです。私が、感染症が広がったらダメだ、そればっかり思ってた時です。今考えれば嬉しい話ですよね。そんなことで止めてる場合じゃない。感染拡大に留意しながら少しずつ活動再開しています。
自分たちの街で他の人が幸せになっていくことを喜ぶ人たちいることがすごく嬉しいです。

──今コロナでたくさんの方が心病んでいます。再開された活動の中で見えてきた課題は何ですか?
勝部:これまで地域で高齢者やいろんな人たちの見守りをしてきたのですが、今、子供に目を向ける必要があることが分かってきました。これまで子供食堂をしていたのですが、子供食堂に来ることができるのは、本人に情報がちゃんと届いている子たちです。だからアウトリーチが必要です。
それで「フードバンク」という取り組みを始めました。食材を届けるっていうアウトリーチなんですが、いろんな方から喜ばれています。
子どもの貧困は教職志望だった私の原点でもあります。スタートラインに立てない子たちを見守ることができる街にしていくっていう観点で、これからは子どもたちに対する食のアウトリーチを続けていきます。子どもって家庭があるから大丈夫って安心しがちだけど、それが崩れてつらい状況にある家庭がたくさんあります。そういう問題に新たなチャレンジをしていきたいです。
それで「フードバンク」という取り組みを始めました。食材を届けるっていうアウトリーチなんですが、いろんな方から喜ばれています。
子どもの貧困は教職志望だった私の原点でもあります。スタートラインに立てない子たちを見守ることができる街にしていくっていう観点で、これからは子どもたちに対する食のアウトリーチを続けていきます。子どもって家庭があるから大丈夫って安心しがちだけど、それが崩れてつらい状況にある家庭がたくさんあります。そういう問題に新たなチャレンジをしていきたいです。

知ろうとしないと見えない

──今日は沢山の学びをいただきました。最後に、私たちに何かメッセージをいただけませんか
勝部:お伝えしたいことは2つあります。一つは知ることによって優しさが生まれるという事。悪意はなくとも「知らないからどう対応していいかわからなかった」。そこから生まれる差別もあります。だから積極的にいろんなことに関心を持って自分の知識を増やすことが重要です。
もう1つは、厳しい人を見捨てない事。そういう人たちを無視することは、自分たちも見捨てられる社会をつくることと同じです。いちばん厳しい状態にある人たちを見捨てない、これがいい社会につながっているのだと思います。
これからの社会は難しいですよね。世の中の価値観が大きく変化していく局面です。こんな時は、力を合わせて生きていくことがすごく大事なのだと思います。
もう1つは、厳しい人を見捨てない事。そういう人たちを無視することは、自分たちも見捨てられる社会をつくることと同じです。いちばん厳しい状態にある人たちを見捨てない、これがいい社会につながっているのだと思います。
これからの社会は難しいですよね。世の中の価値観が大きく変化していく局面です。こんな時は、力を合わせて生きていくことがすごく大事なのだと思います。
──今のお話を聞いて、私たちに見えていなかったものをたくさん発見できました。社会の問題を見つめる上で大切なことってなんでしょうか
勝部:本当のことは、見ようとしないと見えないんです。これは学生時代に西成にインターンに行った時に非常に強く感じたことなのですが…
朝8時半に西成の支援機構に出勤すると、おっちゃんたちが朝からお酒飲んでごろごろしているんです。日雇いで働きたいって口では言いながら、朝から酒飲んでる。最初は「なんやねん、この人ら」って思っていました。
先輩職員さんにその話をすると、「この街は深夜から動いてんねんで。本当の事は朝3時に来ないと分からないよ」って言われたんです。それで3時に行ってみると、そこには日雇いの人工集めの現場がありました。みんな深夜から仕事をもらうために集まって来ているのですが、そこは弱肉強食の世界。体の大きい人とか元気な人がどんどんワンボックスカーに乗せられていって、身体の細い人や年を取って見える人は結局8時になっても雇われない。そして朝方、最後に残った人たちは、お酒を飲んで眠りにつきます。その場面を私は見ていたんです。本当のことは見ようとしないと見えないんだと思いました。
うちの職員も、いろんな地域の現場体験に出します。例えば総務にいる人は総務だけやらせるんじゃなくて、住民が見守りしているところに一緒に行ってもらいます。そうすると、地域を支えているのはこの人たちで、自分たちの仕事はそういう人をバックアップしてるんだってことに気づきます。
市役所もそうです。苦情を言ってくる市民対応だけでなく、実際に自分たちが作った配り物を一生懸命にポスティングしてくれている地域のボランティアさんの動きを見ることでもっと一体感を感じていただけるんじゃないかと思います。
是非、いろんな現場でボランティア活動や、地域で様々な役割を担ってる人たちと出会っていただくような研修も取り入れていただけるといいと思います。是非そういう機会を作ってもらえたら、世の中がもっとよく見えてくるかもしれません。
地域でいろんなことを見ていくと、困りごとが発見できます。そういった困りごとを解決する普遍的な方法ってなんだろ、って考えていくことで次の社会に必要な仕事を見つけることができるんじゃないかなって思います。
朝8時半に西成の支援機構に出勤すると、おっちゃんたちが朝からお酒飲んでごろごろしているんです。日雇いで働きたいって口では言いながら、朝から酒飲んでる。最初は「なんやねん、この人ら」って思っていました。
先輩職員さんにその話をすると、「この街は深夜から動いてんねんで。本当の事は朝3時に来ないと分からないよ」って言われたんです。それで3時に行ってみると、そこには日雇いの人工集めの現場がありました。みんな深夜から仕事をもらうために集まって来ているのですが、そこは弱肉強食の世界。体の大きい人とか元気な人がどんどんワンボックスカーに乗せられていって、身体の細い人や年を取って見える人は結局8時になっても雇われない。そして朝方、最後に残った人たちは、お酒を飲んで眠りにつきます。その場面を私は見ていたんです。本当のことは見ようとしないと見えないんだと思いました。
うちの職員も、いろんな地域の現場体験に出します。例えば総務にいる人は総務だけやらせるんじゃなくて、住民が見守りしているところに一緒に行ってもらいます。そうすると、地域を支えているのはこの人たちで、自分たちの仕事はそういう人をバックアップしてるんだってことに気づきます。
市役所もそうです。苦情を言ってくる市民対応だけでなく、実際に自分たちが作った配り物を一生懸命にポスティングしてくれている地域のボランティアさんの動きを見ることでもっと一体感を感じていただけるんじゃないかと思います。
是非、いろんな現場でボランティア活動や、地域で様々な役割を担ってる人たちと出会っていただくような研修も取り入れていただけるといいと思います。是非そういう機会を作ってもらえたら、世の中がもっとよく見えてくるかもしれません。
地域でいろんなことを見ていくと、困りごとが発見できます。そういった困りごとを解決する普遍的な方法ってなんだろ、って考えていくことで次の社会に必要な仕事を見つけることができるんじゃないかなって思います。
──たくさん宿題をいただきました。本日はありがとうございました。

豊中市社会福祉協議会
〒560-0023 大阪府豊中市岡上の町2-1-15
聞き手:小西敏仁(ネッツトヨタニューリー北大阪 代表取締役社長)
撮影・構成:広報室 山本一夫
撮影・構成:広報室 山本一夫